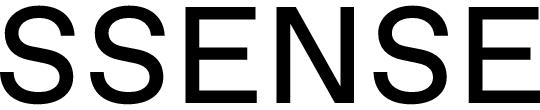Sashiko Galsの夢と挑戦
東日本大震災後に復興支援プログラムとして誕生した岩手県大槌町の刺し子集団は、伝統文化で地元経済の刺激と新たな未来づくりを目指す
- 文: Hyunji Nam
- 写真: Ryosuke Yuasa

「これ、足袋みたいだね!」と、Martin Margielaのタビブーツを目にした刺し子ギャルズ(Sashiko Gals)のメンバーが驚きの声を上げた。Margiela 1989年春夏コレクションに登場して話題をさらった足袋型トゥのデザインが、今や伝説のハイファッションだとは知る由もない。どう見たって、おばあちゃんの世代が履いていた足袋みたいだ。

海沿いの小さな町、大槌。冒頭の画像:刺し子をほどこしたNew Balanceのスニーカー。

東京から列車で北へ3時間の岩手県大槌町。2011年3月11日に東北地方を襲った津波によって、地元経済は甚大な被害を被った。そして今年、地域の高齢女性の経済的自立を目指して発足したのが、Sashiko Gals プロジェクトだ。メンバーは40~80歳の女性15名。母や祖母が多い。
針と糸と端切れさえあればできる刺し子だが、刺し子の手刺繍をほどこされた遊び心のあるスニーカーは一躍バイラルになり、日本のみならず、世界のファッション人種の注目を浴びるようになった。刺し子職人が長時間をかけて仕上げる1点物の特注デザインだから1足20万円の値がつくが、それでも引く手あまたの人気ぶりだ。
刺し子は、元来、幾何学模様の縫い目によって生地の補強や修繕を行う方法だった。500年以上前の江戸時代中期から日本に伝わる実用的な伝統技術は、しかし、不完全さのなかに美を見出す「侘び寂び」の精神と相まって芸術の域へ進化した。そして今、日本の伝統に注目することで有名な東京のデザイナー ストア「KUON」が刺し子を変革し、Sashiko Galsを現代ファッションの世界へ紹介することに成功した。
Sashiko Galsは、新たに得た勢いを次世代へ繋ぎたいと願う。その一環として、5月から地元の商業高校で刺し子の授業を行ない、伝統技術の保存と同時に、若者たちのために職業機会の創出を目指す。

Sashiko Galsのメンバー。

SSENSEの委託によって刺し子をほこどされたMargielaのタビブーツ。
SSENSE:今年はSashiko Galsの人気が急上昇でしたね。チームの皆さんの反応はいかがですか?
今年の3月からスタートしたプロジェクトですが、世界中から反響をいただいて本当に驚いています。たくさん作れるものではないので、多くの方にお待ちいただいている状況です。でも、「待つ」ということも手仕事の魅力として、楽しんでいただけていると思います。
現在、Sashiko Galsのメンバーは何名ですか?
メンバーは15名です。刺し子職人兼事務局員が2名と、刺し子職人が13名。それぞれの得意な刺し子があるので、仕事やプロダクトの内容によって振り分けています。KUONの運営会社であるMOONSHOT社との共同事業なので、刺し子職人は手仕事に専念し、KUONがデザイン監修などを行ない、事業としての戦略からプロモーションなど、刺し子以外の面はMOONSHOT社が担当しています。

細かい手作業に励むSashiko Gals。
刺し子の歴史と特徴について教えてください。
刺し子は、500年前の江戸時代中期から日本に伝わる伝統技術です。東北地方のイメージが強いですが、庶民が衣類を補強したり繕ったりする方法として、自然に日本各地へ広まりました。その後次第に日本人特有の手の器用さと美意識が合わさり、世界でも珍しい手芸文化として、また民衆文化として発展しました。今で言うストリート文化ですね。刺し子の幾何学模様と実用美は、単なる機能を超えて、いつの時代にも通用する文化になっています。

地元の高校生と、刺し子の授業で複雑な模様を刺繍したConverseのスニーカー。


Sashiko Galsが刺し子をほどこした日本の人気キャラクターたち。

カメラに向かってポーズをとる、刺し子を習っている高校生。
Sashiko Galsのメンバーが高齢化していく中で、活動を継続していくための計画はありますか?
これまで伝えられてきた文化や歴史を未来へ繋ぐために、次世代の育成に取り組んでいます。その一環として、大槌町の隣町の商業高校と連携し、授業として刺し子の技術や歴史を教えています。これにより、地元に新しい産業をつくることが目的のひとつです。また、刺し子は「糸と針」があれば「いつでも、どこでも、どなたでも」始めることができるので、このフォーマットを日本中に広げたいと思います。
10年以上の技術をもった刺し子職人でも、スニーカーを1足仕上げるには30時間程度かかります。刺し子は手先に手中するので、1日3時間くらいが限界ですから、1足あたり3週間を要するわけです。そのことを正しく発信し、正しく価値が評価される仕事として持続的に成立させることで、次世代が現実的な希望を持てる職業にしたいと思っています。SASHIKO GALSはブランドではなく、世界に誇れる素晴らしい刺し子技術をもった集団のプロジェクトです。自らをブランド化するよりは、コラボレーションを行なう企業やブランドの価値をあげる存在でいたいと思います。

Sashiko Galsの仕事場。

古くなったものを美しく修繕する方法としても使われる刺し子は、現在のサステナビリティファッションの方向性とも合致していますね。Sashiko Galsは、サステナビリティをどう考えていますか?
日本には古くから「ものを大事にする」、「あらゆるものに神が宿る(八百万の神)」という思想があります。ですから、Sashiko Galsにとって、サスティナビリティはとても自然なことです。例えば、とても気に入っていたComme des Garçonsのスニーカーが古くなって履けなくなってしまった、と持ってこられたお客様がいらっしゃいます。それを刺し子とボロ生地で補強をしたら、新品のような張りが戻りました。これはとてもとても素晴らしい出来事でしたし、同時に履けるアートとしての新しい価値を付加できたことも嬉しかったです。

刺し子を習う高校生と、刺し子で刺繍したドラえもん。
児島のデニムや鯖江の眼鏡など、日本の職人技術は世界で高く評価されています。Rick OwensやLemaireは日本産デニムを使用しているし、Visvimをはじめとする日本ブランドも 刺し子の技法を多用しています。同じように刺し子が世界に認められるためには、何が必要だと思いますか?
国際的な成長には、刺し子を従来のイメージからさらに進化させることが必要です。私たちが、スニーカーやぬいぐるみなど、従来刺し子のイメージになかった分野に挑戦しているのも、そのためです。そうすることで、刺し子を使いたいと思う企業やブランドが増えるでしょう。将来的には、児島や鯖江のように、大槌や東北に「刺し子」の町をつくりたいです。適切なフォーマットやシステムを構築し、日本が誇る技術として刺し子を位置づけることが私たちの目標です。

刺し子で美しく再生したさまざまなブランドのスニーカー。
Sashiko Galsは東日本大震災復興支援プログラムとして立ち上がったプロジェクトですが、13年が経過した今、地域やコミュニティの復興はどんな状況ですか?
まだまだ復興の道半ばです。人口の減少が続いており、若い世代は地元に残りたくとも仕事がなく、大都市に働きに行かざるを得ない人が多いです。Sashiko Galsの立ち上げは、この問題に取り組むことも目的のひとつでした。つまり、地元の産業を育成することで、住民が地元に留まれるようになります。復興は、単なる再建ではなくて、地域社会にとっての持続可能な未来を作り出すことですから。
日本や海外から届いたコメントの中で、特に印象に残っている言葉はありますか?
どれも素晴らしい称賛や応援のコメントですが、「自分も刺し子をやってみた」という写真が特に嬉しいです。
- 文: Hyunji Nam
- 写真: Ryosuke Yuasa
- プロダクション: Hawk Kim / WCS.inc
- 翻訳: Yoriko Inoue
- Date: December 17, 2024